-
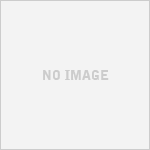
-
双葉の里
2021/06/21
Christian Pilgrimage tour1939年(昭和14)、前人未到の69連勝を達成し、全勝優勝8回・通算優勝12回という成績を 残した宇佐市出身の名横綱・双葉山定次。 歴史ミュージアムシティUSAの西の玄関口に位置する観光拠点のこちらでは彼の生家が 復元され、幼い頃よく遊んだという浜辺には記念碑や相撲場があります。館内には、化粧まわし などが展示された資料展示室、特産品販売所などの施設があります。休憩所では連勝当時の 対戦映像が放映されており、湯茶の接待でお迎えします。 …
-

-
城井1号掩体壕
2021/06/21
Christian Pilgrimage tour宇佐海軍航空隊は1939年(昭和14年)、練習航空隊として開隊しました。しかし、米軍の空襲を うけるようになった1945年(昭和20年)の太平洋戦争末期には特別攻撃隊の基地となり、多くの 若者が南の空に飛び立っていきました。 掩体壕とは軍用機を敵の空襲から守るための施設です。柳ヶ浦地区を中心とした基地の規模は東西 1.2km、南北1.3kmで、184haありました。戦後、飛行場などのあとは、水田や道路にかえされて おり、その面影を残すの …
-

-
福澤諭吉旧居
2021/06/22
Christian Pilgrimage tour福澤諭吉は大阪で誕生(1835)し、1歳で母の実家中津に帰郷しました。 蘭学を学ぶために長崎へ行く19歳までを過ごした家です。母屋や勉強部屋の土蔵などが残り、 隣接する記念館には『学問のすゝめ』の版本や遺品、新旧2枚の一万円札の1号券を展示 してあります。 福澤諭吉は慶應義塾大学の創設者であり伝染病研究所(現:東京大学医科学研究所)や 土筆ヶ岡養生園(現:東京大学医科学研究所附属病院)の創設にも尽力しています …
-
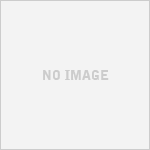
-
羅漢寺
2021/06/22
Christian Pilgrimage tour耶馬渓の荒々しい岩山・羅漢山の中腹に位置する羅漢寺。今から1300年以上前、645年 (大化元年)にインドの僧侶・法道仙人がこの地で修行したことが羅漢寺の始まりと されています。 リフトもしくは少し急勾配な参道を10分ほど歩くと、羅漢山の岩腹に張り付いたように 建てられた厳かな本堂にたどり着きます。羅漢(らかん)とは、釈迦の悟りを得た弟子達のこと。 その姿を彫った日本最古である五百羅漢は、笑っていたり泣いていたりとさまざまな表情を 見せ …
-

-
耶馬渓 競秀峰
2021/06/22
Christian Pilgrimage tour耶馬渓を代表する名勝で、山国川下流側から一の峰・二の峰・三の峰・恵比須岩・大黒岩(帯岩) ・妙見岩・殿岩・釣鐘岩・陣の岩・八王子岩などの巨峰や奇岩群が約1キロに渡り連なっていて、 その裾野には青の門が穿たれています。競秀峰の名は1763年(宝暦13年)に訪れた江戸にある 浅草寺の金龍和尚に命名されましたが、1818年(文政元年)に訪れた頼山陽が描いた水墨画の 代表作「耶馬渓図巻」によって天下に紹介されました。 …
-

-
中津城
2021/06/22
Christian Pilgrimage tour黒田官兵衛(孝高)によって築かれた城で、完成させたのは細川忠興といわれます。 今治城や高松城と並ぶ日本三大水城のひとつに数えられています。本丸上段にある石垣には 黒田氏時代のものを細川氏が拡張した継ぎ目が見られます。黒田氏時代に築かれた石垣は、 現存する石垣としては九州最古のものです。江戸時代中期に奥平昌成が中津藩主となり、 明治維新まで奥平家の居城となりました。1964年(昭和39年)には旧藩主奥平家が中心となり、 市民らの寄付を合わ …
-
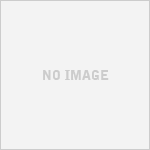
-
両子寺
2021/06/22
Christian Pilgrimage tour国東半島の中心にある六郷満山寺院で、開基は718年(養老2年)仁聞菩薩によるものです。 特に江戸時代より総持院として満山寺院を統括してきました。山門に安置されている仁王像は 国東最大のもので、その彫りの美しさから、国東半島を代表する仁王像であるといわれています。 護摩堂の本尊は鎌倉時代の不動明王で毎月28日の縁日には、護摩焚きがあり、特に厄除けなど 諸祈願を行っています。また、奥の院本殿に祀られている十一面千手観音、両所大権現は古来 よ …
-

-
古式手打ちそば泉
2021/06/21
Christian Pilgrimage tour目の前に金鱗湖が見える古民家造りの食事処です。殻付きそばを、その日使う分だけ 石臼で挽く玄蕎麦の十割そば。由布岳の地下水を備長炭でろ過した水を使用しています。 人気は鴨とねぎの相性抜群の「鴨せいろ」せいろ2段で一人前なのでボリュームあります。 甘味はそばがき黒蜜かけやぜんざいあります。 基本情報 ・住 所 大分県由布市湯布院町川上1269-1 ・アクセス 金鱗湖の畔 湯布院の地図 …
-
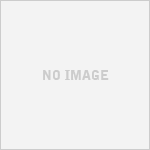
-
熊野磨崖仏
2021/06/22
Christian Pilgrimage tour鬼が一晩で積んだという、険しい石段を登った先にあるのが熊野磨崖仏です。 日本最大級の磨崖仏は、国指定の重要文化財で、平安時代の末期の作といわれています。 絶壁の右手に引き締まった表情の「大日如来(約6.7m)」、左手に微笑んでいるかのような 「不動明王(約8m)」がそれぞれ刻まれているのですが、その姿は余りに自然で、まるで 以前からそこにあったかのように周囲の風景に溶け込んでいます。 熊野磨崖仏入口 大日如来 …
-

-
泉山磁石場
2021/06/29
Christian Pilgrimage tour有田焼の原料となる陶石の採掘場です。江戸時代初期の1616年(元和2年)、朝鮮人陶工・李参平 により発見され、日本で初めて磁器が誕生しました。 400年もの時をかけて、ひと山のほとんどを掘り尽くしたとされる山は扇形に削り取られ、鋭利な 岩肌が剥き出しとなっています。日本の磁器生産に関わる遺跡として国の史跡に指定されました。 現在は休鉱中で採掘されておらず、磁石場が見学できる公園となっています。 採掘をした後の …
